はじめに
電気代の上がり方や気候変動のニュースを見て、安心して長く使えるクリーンな電気がほしいと感じる人は多いです。けれど、専門用語が多くて難しく見えると、情報を追うのが大変ですよね。この記事では、核融合発電を中学生でも読める言葉でまとめます。読むと、核融合発電の基本、今どこまで進んでいるか、実用化までの壁と解決の方向がわかります。結論を先に言うと、核融合発電は燃料が豊富で、発電中に二酸化炭素を出しにくく、長く強く放射線を出すごみが少なくなる見込みがあるため、世界中で研究と投資が加速しています。時間はかかりますが、確実に前に進んでいます。
なぜ今、核融合発電なのか
化石燃料は価格が大きく上下し、燃やすと二酸化炭素を出します。再生可能エネルギー(太陽光や風力)はとても大切ですが、天気や時間に左右され、電気の量が一定になりにくい弱点があります。核融合発電は、太陽で起きている反応を地上で安全にコントロールして、大きなエネルギーを取り出す方法です。もし実用化できれば、安定した電気と脱炭素の両方をねらえるため、注目が集まっています。電気を長く安定して作れる発電所は、工場やデータセンター、電車や病院など、止めたくない場所にとても向いています。
しくみを一言で
核融合発電は、水素どうしをとても高い温度と圧力でくっつけます。くっついたときにエネルギーが出るので、それを電気に変えます。太陽の中で起きていることを、地上の装置でまねするイメージです。装置の中で作られる超高温の気体をプラズマと呼びます。プラズマは触れると装置が壊れてしまうので、壁に当たらないように、強い磁石で空中に浮かせるようにして閉じ込めます。ここで使う強い磁石には、とても冷やすと強くなる超伝導の磁石(とても冷やした強力な磁石)が活躍します。
核融合発電のいいところ
-
燃料が豊富 海水から取り出せる重水素が使えます。世界の多くの場所で手に入るので、国ごとの偏りが小さくなります。
-
二酸化炭素をほとんど出さない 発電中に二酸化炭素を出しにくいので、地球温暖化対策に役立ちます。
-
ごみが少ない見込み 核分裂発電に比べて、長い時間強い放射線を出すごみが少なくなる見込みです。処理の負担が軽くなると期待されています。
-
安定した大量電力 天気に左右されにくく、長い時間にわたって電気を作り続けられる可能性があります。
-
エネルギー安全保障に貢献 燃料の供給が広く、特定の地域に偏りにくいので、国や地域の安心につながります。
-
止めやすく安全設計にしやすい 反応を続けるには条件が必要で、条件を外すと反応が止まりやすい性質があります。コントロールしやすいのは安全面で大事なポイントです。
身近なたとえでイメージ
核融合は、キャンプファイヤーを維持するのに少し似ています。乾いた薪(燃料)をちょうどよい量で入れて、空気(条件)を管理すると火は安定します。水をかけたり、薪を入れなければ火は自然と弱まります。核融合も、燃料や条件をコントロールすることで、反応を続けたり止めたりできます。勝手に暴走しにくいのが大事な特徴です。
世界の主なプロジェクト
-
ITER フランスで建設中の国際実験炉です。大きな出力の核融合を試し、装置や材料が長く使えるかを調べます。
-
SPARC アメリカのCFSとMITが進めるコンパクトな装置です。強い磁石を使い、早い実証をめざしています。
-
Wendelstein 7‑X ドイツの装置です。複雑な形の磁場でプラズマを安定させるやり方に挑戦し、長い時間の運転に強みがあります。
-
NIF アメリカのレーザー核融合施設です。とても強いレーザーを一気に当てて燃料を押しつぶし、エネルギーを取り出す方法を研究しています。
どのプロジェクトも、装置の形、材料、制御の方法を工夫して前に進んでいます。世界中で同時にいろいろなやり方を試すことで、良い方法を見つけるスピードが上がります。日本でも、大学や研究機関で実験が続いており、材料開発や計測技術などで強みがあります。
実用化までのハードル
-
長い時間の安定運転 プラズマがゆらいだり、熱が偏ったりすると装置がうまく働きません。安定して反応を続けるコントロールが必要です。
-
コストの引き下げ とても強い磁石(超伝導マグネット)や、真空容器、冷却設備などは高価です。長く使えて壊れにくい設計にして、発電コストを下げる工夫が必要です。
-
材料の傷みへの対策 反応で生まれる中性子が装置に当たると、材料がだんだん傷みます。傷みに強い材料や、定期的に交換しやすい構造が大切です。
-
メンテナンスのしやすさ ロボットや遠隔操作で部品を交換できるようにするなど、止める時間を短くする工夫が求められます。
-
ルールづくりと地域との対話 安全基準、許認可、避難計画、情報公開など、社会に広げるための仕組みを整える必要があります。
-
電力市場で通用する信頼性 電気を安定して売れるだけの稼働率と、トラブルが少ない運転が必要です。保守計画や予備部品の体制も重要です。
生活と産業にもたらすこと
核融合発電が広がると、工場やデータセンター、鉄道、病院などで使う大量の電気を安定して確保しやすくなります。停電のリスクが下がれば、製品の不良やサービスの停止も減らせます。地域の近くでクリーンな電源をつくれれば、送電ロスが減り、地元の雇用も増えます。さらに、安定で安い電気は、電気自動車の普及や、二酸化炭素を出さずに作る水素(グリーン水素)のコストを下げる助けにもなります。新しい産業が生まれるきっかけにもなります。
よくある不安とその答え
-
危なくないのか 条件が外れると反応は自然に弱まります。止めるための仕組みも重ねて設計します。安全確認は段階的に行われます。
-
ごみはどうするのか 長く強い放射線を出すごみは少なくなる見込みです。材料の選び方や処理の方法を研究し、負担を小さくしていきます。
-
いつ使えるようになるのか 実証機→初期の商用機→改良版という段階で進む見通しです。時間はかかりますが、実験の成功が積み上がっています。
-
家の近くにできるのか 立地は安全基準や送電の事情で決まります。地域との話し合いと情報公開が前提です。
ミニ辞典
-
プラズマ とても高温で、電気を通す気体の状態。装置の中で浮かせて閉じ込めます。
-
超伝導の磁石 とても冷やすと電気の抵抗がほぼゼロになり、強い磁石になれる特別な線材。
-
中性子 反応で飛び出す小さな粒。材料に当たると少しずつ傷めます。
-
稼働率 発電所が働いている時間の割合。高いほどたくさんの電気を安定して作れます。
よくある誤解と今後のながれ
核融合発電は魔法の電源ではありません。スイッチ一つで何でも解決、というわけではないのです。実用化には、技術の確認、コストの引き下げ、ルールづくり、地域との対話が欠かせません。とはいえ、実験の成果と投資が増えていて、実証機→初期の商用機→改良版の商用機という順番で進む見通しが強まっています。長いマラソンのように、着実に距離を重ねている段階です。
まとめ 行動の提案
核融合発電は、地上に小さな太陽をつくる大きな挑戦です。安定した電気と脱炭素を同時にねらえる力があり、生活と産業の両方を支える土台になりえます。最新の動きを追いかけることは、技術の進み具合を正しく見る近道です。次のステップとして、関連する記事(再生可能エネルギーとの役割分担、データセンターの電源の将来像、グリーン水素の作り方とコストの考え方など)も読んで、理解を広げてください。ニュースレターの登録や、エネルギー関連サービスの比較ページも用意しているので、情報収集に役立ててください。

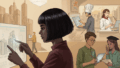

コメント